ホーム > 市政情報 > 計画・取り組み・行政運営 > 政策・調整 > ナッジに関する取組
最終更新日:2026年2月1日
ナッジに関する取組
福井市では、市民サービスの向上や行政運営の効率化を目的として、ナッジ理論を取り入れた政策づくりを行っています。
新着情報
- 【メディア掲載】福井市のナッジが情報誌「地域づくり」に掲載
- 【事例】ナッジ理論を取り入れた「カスハラ防止啓発ポスター」を作成
- 【事例】ナッジ理論を取り入れた「自治会加入促進ポスター」を作成
- 福井市のナッジの取組が定期監査にて「良好事例」と高評価!
福井市のナッジ事例
セミナー情報
- 「ナッジ×ゲーミフィケーション」セミナー(R8.1.20開催 ※終了しました)
- 「デザイン思考+ナッジ」セミナー(R7.1.21開催 ※終了しました)
- 「ナッジまるわかり!○△□(まるさんかくしかく)教室」(R6.1.30開催 ※終了しました)
表彰実績
掲載実績
- 「職員の提案から生まれたナッジ・ユニットー大腸がん検診の受診率向上にー」(一般財団法人 地域活性化センター「地域づくり」2026年2月号)
- 「『ハガキのデザイン』で市民の行動が変化、なぜ?―福井市のナッジ施策が光る”がん検診”の工夫―」(ITmediaビジネスオンライン,2025年4月)
- 「ナッジの政策活用― 自治体組織内へのナッジの普及プロセス―」(一般社団法人 行政情報システム研究所「AIS Online」2025年4月号)
- 「自治体組織内へのナッジの普及プロセス」(一般社団法人 行政情報システム研究所「課題解決ツールボックス」2024年11月)
ナッジ検討ツール
ナッジの検討を行うにあたっての基本的な検討プロセスを示すツールキットを無料公開しています。
福井市ナッジ・ユニットを結成しました
令和5年4月、本市政策へのナッジの普及促進を担う若手職員有志チーム「福井市ナッジ・ユニット」を結成しました。
これは、前例にとらわれない新しい価値観や柔軟な発想に基づく事業を予算化する「チャレンジみらい予算」制度により、ナッジに関心を持つ20~30歳代の職員7人が市へ提案し、実現に至ったものです。
ナッジ理論とは?
ナッジ(nudge…そっと後押しする)とは、行動科学の知見の活用により人々が自分や社会にとってより良い選択を自発的にとれるように手助けする政策手法のことです。
このナッジ理論は2017年にノーベル経済学賞を受賞したことで大きな注目を集めています。
詳細は環境省ホームページ「ナッジとは?」をご参照ください。
ナッジを活用するメリット
(1)費用対効果が高い
これは地方自治法第2条第14項にある「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」との規定のとおり、公共サービスの効率化を図る上で望ましい政策手法であると言えます。
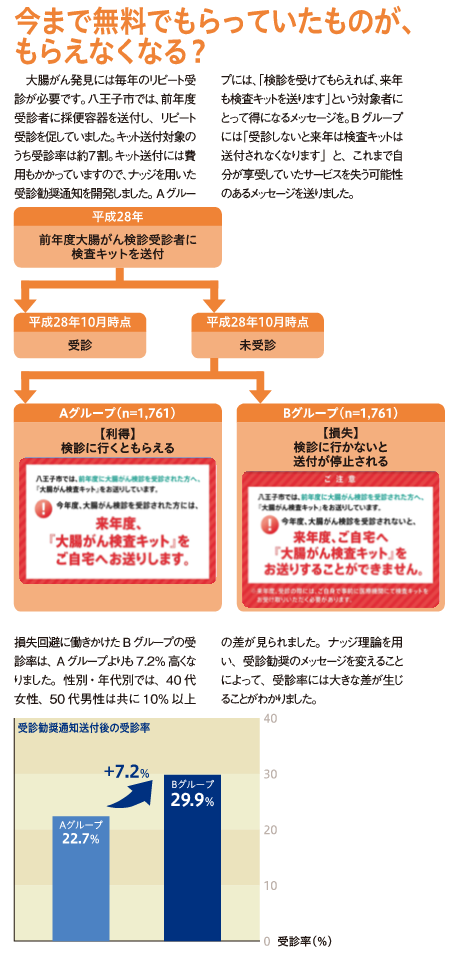
(2)あらゆる公共政策分野に応用しやすい
ナッジは人の行動を変えるための取組に活用できるため、「健康行動を後押しするには?」や「環境に良い行動を促進するには?」など、行政が行う業務と相性が良いと言えます。特に、市町村の業務は住民の行動と密接に関わることが多いためナッジ活用の余地が大きいです。
(3)職員の政策立案スキルの向上
お問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283 | ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:026413


